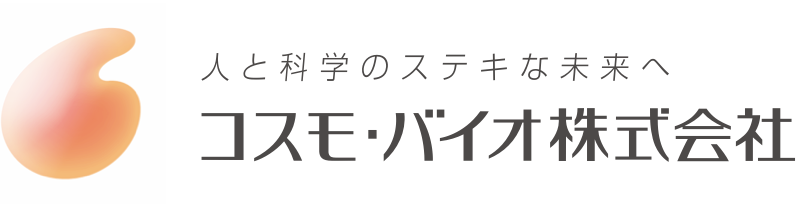サステナビリティ
Biodiversity and Chemistry in KOSEN
- 生物の不思議を調べてみよう!-
2018年度 第15回 公開講座応援団
和歌山工業高等専門学校 生物応用科学科 公開講座レポート
平成30年8月6日に和歌山工業高等専門学校 (Part 1)、9月8日に県民交流プラザ・和歌山ビッグ愛 (Part 2)、9月29日に和歌山工業高等専門学校 (Part3) にて、公開講座「Biodiversity and Chemistry in KOSEN -生物の不思議を調べてみよう!-」が開催されました。3つの講座で生き物が持つDNA やタンパク質の実態及びその働きを理解し、地球の生物や自然を身近に感じてもらうとともに、それらを理解するために使われる分析技術を学ぶことで科学技術に興味を持ってもらうことを大きなテーマに掲げ、対象学年に合わせた様々な実験を行いました。対象学年は「小学高学年~中学2 年生」、「中学1・2 年生」、「中学2・3 年生」の3つのPart に分け、それぞれに合ったレベルでの体験型公開講座を開催しました。その様子をレポートにまとめました。
講座内容
Part 1
生物・化学の力を使って犯人をつかまえよう
本公開講座では、架空の事件が起こったと設定し、参加者の方々は鑑識になりきってもらい実験をおこないました。実験は、現場に残されたいくつかの物品(スプーン, フォーク)のうち気になるものを選択し、唾液検出キットを用いて唾液がついているかを判定しました。また、唾液がついている物品について、その唾液の血液型が何かを血液型判定キットを用いて判定しました。さらに、コップの取手(紙コップに写真用紙を切ったものを貼り付けたもの)に指紋の有無をニンヒドリン反応を使って確認しました。それらの結果は、容疑者となっている人物の血液型を示したものと比較し、犯人を特定しました。また、唾液検出キットでは、クロマトグラフィーの原理を用いているため、それを理解してもらうことを目的にろ紙と水性ペンを用いてペーパークロマトグラフィーを行い、原理を説明しました。また、血液型判定では抗原抗体反応、指紋検出ではニンヒドリン反応について説明をおこないました。
実験は目で見てはっきりわかるものばかりで、参加者の方々は出てくる結果に一気一憂しながら楽しんでいる様子が見られました。また、クイズ形式で犯人の特定をおこなったので、正解すると喜び合い、盛り上がる様子も見られました。参加者の方々からは「楽しかった」や「興味深かったのでまたやりたい」といった声も聞かれました。

写真1. 実験の説明を受ける様子

写真2. 証拠物品の一部

写真3. 実験の様子

写真4. 唾液判定結果を観察
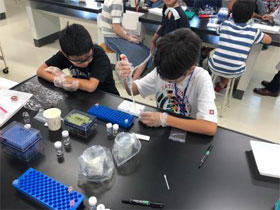
写真5. 血液型判定実験の様子

写真6. ペーパークロマトグラフィー実験
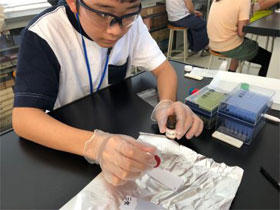
写真7. ニンヒドリン反応実験

写真8. 血液型判定結果を確認する様子
Part 2
生き物がいる環境を生き物がもつ色素から分析しよう
本公開講座では、薄層クロマトグラフィーを用いて植物の光合成色素を分離し、その違いから各植物が生息する環境を予測しました。また、おこなった実験の結果について簡単なレポートを作成してもらいました。まず、クロマトグラフィーの原理を知るために、水性ペンとろ紙を用いた予備実験をおこない、本公開講座の目的である薄層クロマトグラフィーをおこないました。植物試料にはワカメ、アオサ、フノリの各粉末、市販のティーパックの緑茶を用いました。また、緑茶以外の三種類については未知試料とし、各粉末を有機溶媒に溶解してもらい、緑茶については茶葉を乳鉢および乳棒を使ってすりつぶしたものを有機溶媒に溶解し、薄層にスポットしてもらいました。薄層のスポットを展開溶媒につけるとすぐに色素の分離が始まり、参加者の方々はその様子を興味深そうに観察していました。また、保護者の方々も一緒になって観察し、楽しんでいる様子が見られました。未知試料の結果は、緑茶の結果と事前に説明した色素の種類のデータをもとにワカメ、アオサ、フノリのどれに当たるかを考えてもらいました。また、含まれる色素の違いがなぜ起こるのかについて、生息する環境と結びつけて考察してもらいました。結果と考察を含めて、実験レポートの書き方を指導し、実際に参加者らに簡単なレポート作成をしてもらいました。普段、実験の結果を考察し、レポートを作成することがないためか、「考察があってうれしかった」や「もっと知識を増やしたい」といった感想が聞かれました。

写真1. 実験の説明を受ける様子

写真2. ペーパークロマトグラフィーをする様子
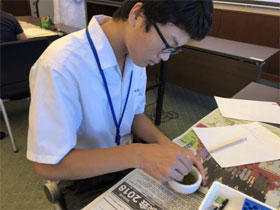
写真3. 試料作製

写真4. 薄層にスポットを作る様子(1)

写真5. 薄層にスポットを作る様子(2)

写真6. スポットの上昇を観察(1)

写真7. スポットの上昇を観察(2)
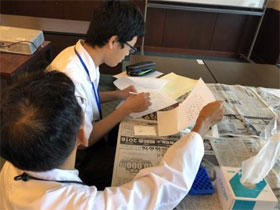
写真8. レポート作成
Part 3
生き物の肉片からDNA を取り出してみよう
本公開講座では、数種類の肉片からDNAを抽出し、電気泳動をおこなって動物の種類によって得られるバンドのパターンが異なることを観察してもらいました。また、動物にも血液型があることを確認するために、スーパーでよく見る魚の血液型を判定キットを用いて判定しました。参加者の方々は、DNAとは何かを知るために、目で確認できる簡単な実験をおこないました。DNAを家にもあるものを使ってオレンジジュースから分離しDNAを確認すると、参加者の方々は興味深そうに観察していました。その後、いくつかある動物の肉片からDNA抽出をおこない、電気泳動をおこないました。オレンジジュースの実験をしたことや、DNAについての詳しい説明は模型を使いながら説明したこともあり、肉片から抽出したDNAは目に見えなくてもDNAのイメージを持って実験に取り組めたようでした。電気泳動後、動物によってバンドの位置が異なることを確認した後、この結果からどのようなことがわかるかについて生物進化の話を交えながら説明を受け考察をおこないました。
さらに、参加者の方々は血液型判定では動物にも血液型があること、抗原抗体反応という自分たちの身体の中でおこっている化学反応を使うと判定できることにも驚いていました。
最後に、これらの実験がどのような研究や技術に生かされるかを紹介して終了しました。参加者の方々からは、「DNAの話に興味を持っていたが、さらに興味が持てた」など嬉しい声も聞かれました。

写真1. 実験の説明を受ける様子

写真2. オレンジジュースからDNAを抽出

写真3. 模型を使って説明を受ける様子

写真4. 血液型判定実験の様子(1)

写真5. 血液型判定実験の様子(2)

写真6. DNA抽出・電気泳動実験の様子(1)

写真7. DNA抽出・電気泳動実験の様子(2)

写真8. 電気泳動の結果を観察する様子
使用商品
公開講座でご使用いただいた商品をご紹介します。
参加者アンケート
Part 1: 生物・化学の力を使って犯人をつかまえよう について
- 指紋や唾液を検出するのは楽しかった。血液型も意外と簡単にわかって驚いた。クロマトグラフィーが利用されていて面白かった。
- 楽しかった。
- 個人情報を大切にしようと思った。
Part 2: 生き物がいる環境を生き物がもつ色素から分析しよう について
- いろいろな実験で生息している場所を導き出すのが楽しかった。
- 自然に対する興味が高まった。また、自分の無知を痛感した。高校でもっと知識を増やしていきたい。
- 考察があってうれしかった。
Part 3: 生き物の肉片からDNA を取り出してみよう
- 今日のことで生物応用化学科に興味を持ち、前々から電気情報工学科にも興味があったので、どちらに入ろうか迷いました。
- とても楽しかったです!今回はどうもありがとうございました。
- DNAの話に興味を持っていたが今日は知らなかったことも知ることが出来たし、さらに興味を持てる話と実験だった。
アンケート結果から
興味づけをした「小学校高学年~中学2年生」では、アンケートの自由記入に次回「DNAを取り出してみたい」や「化石の実験がしたい」といった次のステップへつながる実験の希望もあり、今回の公開講座の目的は達成できたと考えています。
「中学1・2年生」では、自由記入に「考察があってうれしかった」や「導き出すのが楽しかった」といった声もあり、参加者の方々が持っている知識と与えられた情報を実験結果と結び付け考えることを楽しめたと考えています。中学での実験やこれまでの公開講座では、観察や結果を出すことを目的としたものが多く、考察まで行うことがなかった可能性があります。今回のように参加者の方々の想像を結果という事実と知識を組み合わせて論理的に説明する方法も今後の公開講座では取り入れることも良いと感じました。
「中学2・3年生」のアンケート結果では進学について考える学年が対象であったこともあり、小学生~中学1年生とは違い、より真剣に取り組み学ぼうとする姿勢も見られました。その結果、自然科学に対する興味に加え、理解を深められたことが十分にわかる結果となりました。