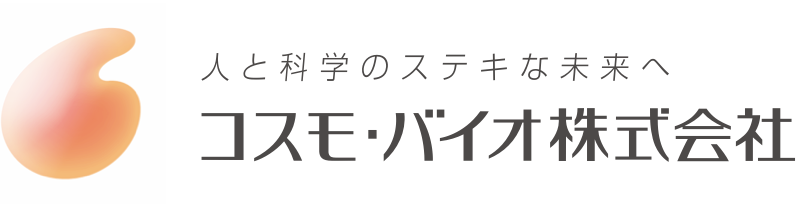サステナビリティ
Biodiversity and Chemistry in KOSEN
- 生物の不思議を 分子レベルで見よう!Part 1, Part 2, Part 3 -
2017年度 第14回 公開講座応援団
和歌山工業高等専門学校 生物応用科学科 公開講座レポート
平成29年7月22日に和歌山工業高等専門学校 (Part 1)、9月9日に県民交流プラザ・和歌山ビック愛 (Part 2)、12月2日に情報交流センター Big・U (Part3) にて、公開講座「Biodiversity and Chemistry in KOSEN - 生物の不思議を 分子レベルで見よう!Part 1, Part 2, Part 3 -」が開催されました。3つの講座で40名の小・中学生が参加し、Part 1 では様々な生物の肉片からDNAを抽出、Part 2 では参加者自らの唾液を用いた血液型判定、Part 3 では唾液および指紋の検出実験を体験しました。その様子をレポートにまとめました。
講座内容
Part 1
生き物の肉片から実際にDNAを取り出してみよう!
DNA 抽出キットを用いて、スーパーなどで売っている良く知った肉片からDNA 抽出体験をします。肉片は数種類用意し、形(見た目)が異なる生き物でも皆 DNA を持っていることについて学びます。さらに、実験後には、DNA 配列を用いる生物多様性とその進化についての講義や議論、様々な生き物の分類体系を作成してもらうなどのアクティブラーニングを実施しました。
取り扱う試薬の量が少量であることや慣れない器具の取り扱いに四苦八苦していた参加者も DNA の増幅が確認できました。この公開講座で生物に興味を持った参加者とその保護者から、公開講座終了後も質問を多くしてもらうなど、好評でした。

写真1. DNA 抽出の説明

写真2. 実験の様子 (1)

写真3. 実験の様子 (2)

写真4. 実験の様子 (3)

写真5. 電気泳動

写真6. 結果説明
Part 2
生き物にはどんな血液型があるのか確認してみよう!
参加者自らの唾液を用いて血液型判定をしてもらい、また未知試料として「ウシ」や和歌山県で漁れた「アジ」の血液の希釈液から血液型を確認し、他の生物にも血液型が存在することを学びます。
参加者らの中には、唾液をマイクロチューブに取り出すことを恥ずかしがったり、必要量がなかなか取れず苦労する参加者もいました。その後の講義で血液型判定の原理にある抗原抗体反応について学び、生体内で起こる化学反応についての理解も深めてもらったあと、参加者自身の血液型と判定結果が合っているかを確認し、判定が合っていたことにほっとしている様子や未知試料の結果を当てて嬉しそうにしていました。小学校高学年~中学生までと幅広い年齢層の参加であったが、参加者同士結果を見せ合い楽しんでいる様子が見られました。

写真1. 実験操作の説明

写真2. 実験の様子(1)

写真3. 実験の様子 (2)

写真4. 実験の様子 (3)

写真5. 実験結果

写真6. 判定結果の解説
Part 3
からだで起こる反応をつかって犯人を捕まえよう!
ある事件現場で押収されたコップとフォークから唾液を、紙からは指紋を検出するという設定で行いました。唾液の検出には RSID™ SALIVA を使用し、指紋はニンヒドリン反応を使って検出しました。また、唾液検出で行われるクロマトグラフィーの原理を理解するために、ろ紙にインクを染み込ませ分離するペーパークロマトグラフィーを同時に行いました。ペーパークロマトグラフィーはインクの成分の分離が目に見えて様子がわかり「きれい」や「おお!」という声が聞かれました。このペーパークロマトグラフィーを行なったあと、唾液検出に使用されているクロマトグラフィーの原理を説明すると、少し難しかったようですが、なんとなくイメージができたようで、しかもそれが体で起こる反応が使われているということがわかり、「すごい」という声も聞かれました。

写真1. 実験操作の説明

写真2. 唾液の拭き取り操作

写真3. 実験の様子(1)

写真4. 実験の様子(2)

写真5. 実験の様子(3)

写真6. 実験の様子(4)
使用商品
公開講座でご使用いただいた商品をご紹介します。
参加者アンケート
Part 1: 生き物の肉片から実際にDNA を取り出してみよう! について
- 生物のDNAについて色々詳しく知れました。
- 実験が複雑で難しかったけど、講義がとてもおもしろかった。
- 生物をDNAでどのように分類するのかがわかった。DNAのこともわかった。
Part 2: 生き物にはどんな血液型があるのか確認してみよう! について
- 血液型が詳しく知れてうれしかったです。
- とても楽しかったです。元々、実験したりするのが好きだったのですが、さらに好きになりました。
- 今日の公開講座で血液型や免疫作用についての興味がより高まりました。
- 血液型の仕組みがどうなっているのか知れてよかったです。
- 知らなかったことがよく知れて楽しかった。また参加してみたい。
Part 3: からだで起こる反応をつかって犯人を捕まえよう!
- DNA 検出もしてみたい。
- 初めて知って友達にも言ってみたいと思いました。
- 色々な事を学べてよかったし、楽しかったです。
アンケート結果から
Part 1 では、初参加の参加者が半数を占めましたが、そのほかの講座ではこのような公開講座に参加したことのある参加者が多く、これまでに行ってきた活動では科学に触れる機会を与えられることを目的としてきたが、科学に興味を持った小・中学生が増えてきていると考えられます。ほとんどの参加者が内容がわかりやすくおもしろかったと回答していたことからも、本講座の目的がある程度達成できたと考えています。
今回は、前回よりも講座を多くし、当初、各公開講座の対象学年をPart1:中学生、Part2:小学5 年生~中学生、Part3:小学4年生~小学6 年生とする予定であったが、Part3 については中学生も参加したいということで、小学4 年生~中学1 年生までとしました。しかし、今後誘いたくないとの意見もみられたことから、内容が簡単すぎたことも原因の一つと考えられます。今後は、対象年齢を小学低学年とするなど、対象学年の精査が必要と思われます。
参加者が中学生の場合、本活動は学校からの情報により知ったという意見が多く、中学校へのチラシやポスターなどの配布、中学校の先生への情報提供が周知方法で最も有効な手段であると考えています。また、小学生の場合は家のひとからと言う意見が多く見られ、小学校だけではなく他の周知方法も考える必要があると思いました。
主催者報告
Part 1 および Part 2 ではほぼ定員に達しましたが、Part 3 については定員割れしていないものの参加者の人数が少なかったです。時期が遅かったことや対象学年の主が小学生であること、アンケート結果を考慮すると、学校以外の周知方法を考え実施する必要があると感じました。しかし、その一方で参加者のほとんどが小学生ということもあり、多くの保護者も参加者と一緒に実験をするなど、子供から大人までが一緒になって理解を深められたという点は良かったと考えています。また、人数が少ないことで TA によるサポートが細かなところまでできたことも良かったと感じています。対象に小学生を主とした公開講座については、今後、検討していく必要がある。すべての公開講座では明るく楽しい雰囲気で実施することができた。特にPart 1 やPart 2 では、「楽しい」や「すごい」といった声とともに、「しくみがよくわかった」や「さらに実験が好きになった」という嬉しい意見を聞くことができました。また小学生の多い Part 3 では保護者からも「すごい」という声が多く聞かれたことや、参加者からは「次は DNA 検出もしてみたい」など、次へ繋がる意見も聞け、生物や生物実験への興味を多く持ってもらえたと考えています。
[講師紹介]
和歌山工業高等専門学校 生物応用化学科
准教授 SETIAMARGA, Davin 先生
准教授 西本 真琴 先生