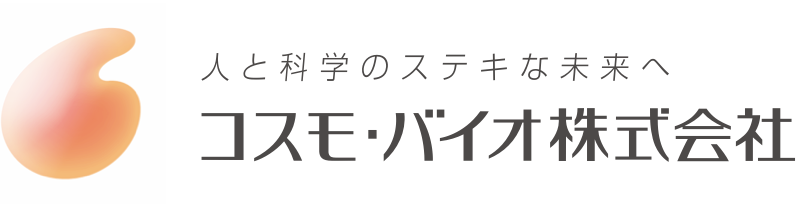サステナビリティ
キャンパスアドベンチャー2009 秋
2009年度 第6回 公開講座応援団
高知工業高等専門学校 公開講座レポート
平成21年11月1日(日)高知工業高等専門学校にて、「キャンパスアドベンチャー2009」子ども科学体験講座(公開講座)が開催されました。
子どもたちに科学やものづくりに、より一層興味や関心を抱いてもらおう!と、実験補助の高専生が丁寧に指導し、同行した家族も楽しめる5つの講座が開催されました。
そのなかでも「生き物の設計図、遺伝子ってなに?」「DNA鑑定!君も犯罪捜査官!」の2つには、生命やバイオテクノロジーに興味を持つ小学6年生から中学3年生の18名が取り組みました。初めて体験するバイオの世界。参加した子どもたちは、実験を通して、“科学”に対する興味は深まったのでしょうか?その様子を公開講座レポートにまとめました。
実験の内容
「生き物の設計図、遺伝子ってなに?」「DNA鑑定!君も犯罪捜査官!」
全ての生き物は「遺伝子(DNA)」という設計図によって形づくられています。今回の講座では、DNAを実際に目で見たり、手で触れたりすることによって興味を持ってもらい、犯罪捜査の手法として利用されているDNA鑑定を通して、遺伝子実験の社会的位置付けについての理解促進を目的といたしました。
実験前に先生の授業です。私たちの体は、細胞が集まって形作られています。この細胞1つ1つには染色体と呼ばれるものがあり、その中に遺伝子情報が入っています。さらに、この情報を持っているものが遺伝子(DNA)と呼ばれる糸状の物質です。さあ、実際にその遺伝子をとって目で見てみましょう。

サケの精巣からDNAを抽出しています。DNAが“白い糸”のようになって目で見ることができました。

DNAには「ガラスにくっつく」性質があるので、ガラス棒を使ってそのDNAを巻き取ります。

つぎにDNA鑑定です!3種類のDNAサンプルを、それぞれ制限酵素で切断して短くします。これをアガロースゲルと呼ばれる高分子ゲルの中に通します。DNAは固有の大きさ(分子量)と荷電を持っているので、電流が流れる「電気泳動装置」の中にアガロースゲルを入れ、DNAを通すと、DNAは分子量の違いによって様々なバンドとなって検出できました。みんな興味津々で説明を聞いています。このDNA鑑定の手法は生物学の研究のみならず、犯罪捜査や親子鑑定、考古学など幅広い分野で応用され、バイオテクノロジーの中でも最もよく知られている技術の一つです。

参加者の感想
今回の公開講座を通じて,参加した子どもたちはどのような感想を持ったのでしょうか?寄せられたアンケートの一部をご紹介いたします。(原文のまま)
- 遺伝子についてよくわかった。
- みんなやさしかった。
- おととしもここにきて、じっけんをしたけど、今日の実験はとてもたのしかった。
- ぬるぬるでびっくりした。
- 高知高専に入りたいと思った。
- 思っていたより内容がむずかしかった。
- さいぼうはきもちわるくて、ぬるぬるしてた。
- DNAってもっと太いかと思ってた。
- さいぼうやDNAのことがよくわかってよかった。
主催者報告
生命やバイオテクロノジーに興味を持つ児童(その保護者)が本講座に集まった様子で熱心な取り組みとなりました。DNA抽出からDNAを目で見て触れることができる驚きやDNA鑑定キットから個人識別が可能なことなど、興味深く、更に生命について学ぼうとする姿勢が垣間見れました。