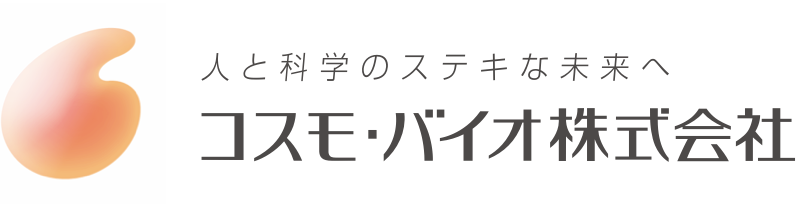サステナビリティ
高校生向け基礎実験体験講座
「がん細胞はくっついて増える!~細胞接着装置を観察しよう~」
2014年度 第11回 公開講座応援団
愛知県がんセンター研究所 公開講座レポート
平成26年7月29日(火)愛知県がんセンター研究所にて高校生向け基礎実験体験講座「がん細胞はくっついて増える!~細胞接着装置を観察しよう」が開催されました。当日は12名の高校生が参加し、若手研究者の指導のもと、免疫蛍光細胞染色を行いました。今回初めて体験する方がほとんどでしたが、皆さん上手に染色することができたのでしょうか?その様子をレポートします!
実験の内容
がんが治りにくい原因のひとつは、がんが周囲の正常組織に浸潤したり、他の臓器などに遠隔転移するためです。このがんの浸潤・転移には、がん細胞同士がくっついている機構である細胞間接着機構が重要な役割を果たしています。本日は、この細胞間接着に関わる代表的なタンパク質であるE-カドヘリンを、免疫蛍光細胞染色という方法を用いて観察します。
実験1 細胞の観察およびEGTA処理
今回、試料となるのは、“ヒト大腸がん由来のCaco-2細胞“です。
- 実験前にディッシュ内の細胞の状態(活きがよいか、増え方に問題がないか、培養液に異常はないか、等)を光学顕微鏡で観察します。コンフルエント(培養面一杯に細胞がいる状態)の一歩手前で実験を始めます。
- カドヘリン依存性の細胞間接着を阻害するために、Ca2+キレート剤であるEGTA溶液40µlをディッシュに加えます。陰性対象として対象として1mMトリス緩衝液40µlをもうひとつのディッシュに加え、ディッシュを回して混和します。
- 37℃インキュベーターで約1時間静置します。
- EGTA添加(-)および(+)の位相差顕微鏡観察を行います。
細胞間接着が非常にダイナミックに制御されていることを実感して頂くために、無処理で正常状態のE-カドヘリンと薬剤処理で接着を破壊した時のE-カドヘリンを観察します。隣り合う細胞は、その表面に出ているE-カドヘリンが結合して接着していますが、この接着には、Ca2+イオンが必要です。細胞をCa2+キレート剤であるEGTAで処理するとCa2+イオンがなくなり、E-カドヘリン同士が結合できなくなります。 実験を検証するための実験を対照(コントロール)実験といいます。今回の実験ではEGTAを溶かしている溶媒である1mMトリス緩衝液(pH8)を同量加えます。
実験2 細胞の固定
- ディッシュ内の培養液を取り除き、700µlの3.7%ホルマリンを加えます。
- 10分間放置後、ホルマリンを除き、PBSで4回洗浄します。
細胞の生命活動を現状で停止させて状態を保存するための操作を固定といいます。固定には目的に合わせて薬剤を選択します。組織の形態を保持する目的ではホルマリンがよく使われています。
実験3 ブロッキング
- PBSを除き、ブロッキング剤(PBS)を500µl加えます。
- 30分間静置します。
抗体が抗原の立体的構造以外の条件で結合(非特異的吸着)する現象をブロッキング剤で防ぎます。安価に調製できる血清アルブミンや今回用いるヤギ血清などが、ブロッキング剤としてよく使われています。
実験4 抗体処理
- ディッシュ内のブロッキング剤を除去します。
- 抗体溶液を500µl加えます。
- 1時間以上静置します。
今回、抗体溶液として、抗原(E-カドヘリン)を認識する1次抗体をAlexaFluor488で標識したものを用います。
実験5 核/DNAの染色の処理
- ディッシュ内の抗体溶液を除去し、PBSで3回洗浄します。
- PBSを除き、DAPI溶液を500µl加えます。
- 3. 15分間静置し、PBSで4回洗浄します。
実験6 共焦レーザースキャン顕微鏡での観察
- PBSが入った状態で観察します。
実験風景


はじめは慣れなかったピペットマンでの操作も、実験をすすめるうちにだんだん上手く使えるようになってきました。
参加者の声
今回の講座で、印象に残ったことや感想を挙げてもらいました。
- 試薬を加え除去する地道な作業を繰り返すうちに、実験には時間が大切なのだと確認させられた。
- 色々な先生方との会話がとてもためになった。
- 細胞染色像を見せてもらったときは感動した。
- カドヘリンが光っているのがとても印象的だった。
- 共焦レーザー顕微鏡で自分たちの実験したものを核と他のもので分けて見られたので分かりやすかった。
主催者報告
免疫蛍光細胞染色では参加者全員が上手く染色することができました。アンケートの結果からも、「体験講座に参加して面白かった」「説明内容もよく理解できた」といった意見が多数を占めており、参加した高校生にはとても好評だったようです。
愛知県がんセンター研究所 腫瘍医化学部
室長 井澤 一郎 先生