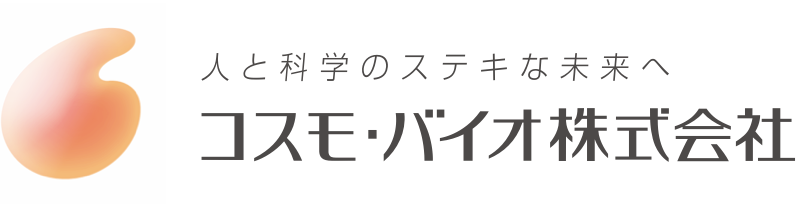サステナビリティ
食べ物の味について調べよう
2013年度 第10回 公開講座応援団
帯広畜産大学 公開講座レポート
小学生の親子および一般人を対象とした公開講座「食べ物の味について調べよう」が下記の日程で開催されました。本講座は、「食の大切さ」を科学的に学んでもらうことを目的としており、参加者は自分の味覚・臭覚の能力を試す4つの実験を行いました。さて、参加した皆さんはどういった実験を行い、味や香りへの理解を深めていったのでしょうか?その様子を覗いてみましょう!!
北海道帯広市児童会館 2013年8月4日(日) 10:00~15:00
北海道帯広市とかちプラザ 2013年12月14日(日) 10:00~15:00
北海道帯広市児童会館 2014年2月2日(日) 10:00~15:00
実験内容
実験1 -5味の識別テスト-
5種の基本味(甘味・塩味・酸味・苦味・うま味)を代表する呈味物質:ショ糖、食塩、酒石酸、硫酸キニーネ、グルタミン酸ナトリウムを用いての感度テストを行います。
【方法】
5種の希薄溶液を入れたコップをランダムに与え、それぞれの味を当ててもらいます(配偶法)。まぐれ当たりの確率を小さくするために蒸留水(無味)の入ったコップを3個入れて計8個のコップの中から5味を当てます。
グルタミン酸ナトリウムの閾値濃度は人により幅があるので、いくつかの濃度の異なる溶液を作製して官能評価を行い、感知できる濃度を測定します。濃度測定には、コスモ・バイオ(株)お取扱いの「グルタミン酸測定キット」を使用しました。
実験2 -味の濃度差識別テスト-
苦味を除く4種の基本味につき、各味ごとに濃度の異なる2つの溶液を比較してもらい、味の強い方を判断します。
【方法】
差が僅少な濃度差の両者を比較して、味の強い方を選びます (2点識別試験法)。4種の呈味物質(ショ糖、食塩、酒石酸、グルタミン酸ナトリウム)の濃度比をとり、甘味・塩味・酸味・うま味の4味の比較判定を行います。
実験3 -デンプンのアミラーゼ処理後における味覚と色調の比較テスト
デンプン水溶液にアミラーゼ活性剤を加えて、味覚の変化を観察します。時間との関連で比較します。またヨウ素液を加えて、デンプン溶液とアミラーゼ処理後の溶液の色調の違いを観察する。ヨウ素デンプン反応による色の変化と味覚の変化を観察します。
アミラーゼ活性剤の能力は、コスモ・バイオ(株)お取扱いの「アミラーゼアッセイキット」にて確認します。
実験4 -臭覚試験-
嗅覚検査は5種類の基準臭を用いてその匂いが嗅ぎ分けられるかどうかを調べるもので、5種類すべてを嗅ぎ分けた人を正常とみなしています。
| A: | β-フェニルエチルアルコール - 花(バラ)の匂い ストック10倍濃縮液の調製;100ml中に0.1ml(100μl) |
|---|---|
| B: | メチルシクロペンテノロン - 焦げ(カラメル)臭 ストック10倍濃縮液の調製;100ml中に0.02ml(20μl) |
| C: | イソ吉草酸 - 腐敗臭・汗臭いにおい ストック10倍濃縮液の調製;100ml中に0.01ml(10μl) |
| D: | γ-ウンデカラクトン - 果実(モモ)の匂い ストック10倍濃縮液の調製;100ml中に0.02ml(20μl) |
| E: | スカトール - 糞臭、口臭 (固体試薬) ストック液の調製;100ml中に0.001ml、5mg精秤し、5mlの蒸留水を加える。 |
【準備】
- 1.各ストック10倍濃度液を1ml取り9mlの蒸留水を加えてA~D検査試薬とします。E検査試薬は10ml中に0.1mgとなるように、0.1ml加え調製します。
- 2.1cm角に切断した脱脂綿に検査試薬1mlを取り、A~Eのジッパー袋もしくはチューブに入れます。
【方法】
臭覚試験:試験者はA~Eの袋の匂いを嗅ぎ、どのような臭いかを選択肢から選び、検査用紙に番号で示します。
公開講座の様子

主催者報告
今回、味と香りを総合的な評価法により学んでもらいましたが、小学生4、5年生以上であれば、自身の舌や鼻の能力チェックをすることの意味がわかるようであった。しかし、低学年には難しいようなので、実施できる範囲のことで楽しんでもらった。例えば、ピペット操作を教えることで、エッペンチューブから溶液を吸って、別のチューブに溶液を移動させる操作などは繰り返し行い、楽しそうであった。マイクロピペットを使う参加者の目は真剣そのものでした。科学のイロハを体感できたのかもしれません。
今回の企画は、味・香りの重要性を広げる目的で行いましたが、食に対して親子で共通の話題として持ち帰ることにより、味覚や臭覚を科学的な理解として、家庭の中まで話題を広げられるプログラムであったと感じています。
帯広畜産大学 畜産学部食品科学研究部門
小嶋 道之 准教授