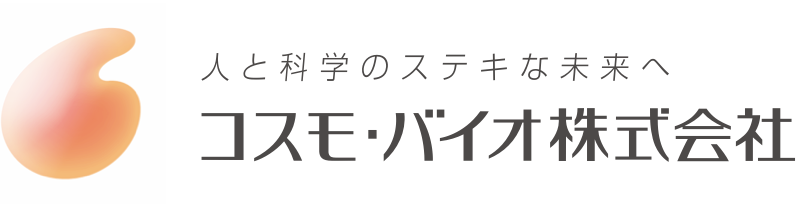サステナビリティ
植物バイオから広がる科学の不思議な世界
2012年度 第9回 公開講座応援団
福岡教育大学 公開講座レポート
2012年8月8日、福岡教育大学自然科学教棟にて、中高生および教員を対象とした公開講座「植物バイオから広がる科学の不思議な世界」が開催されました。午前中のテーマは「植物の機能を生かした科学実験」。比較的やさしい内容のものから始まり、午後は「遺伝子DNAに関する科学実験」というテーマで、内容もかなりレベルアップしたものとなりました。今回参加した皆さんは「科学の不思議な世界」を身近に感じることができたのでしょうか?公開講座の様子をレポートにまとめました。
講座内容
<午前>
植物の機能を生かした科学実験
藍染め編 - 藍染めを体験してみよう -
日本では伝統工芸として多くの染物が知られていますが、その中でも藍染めは古くから野良着やもんぺなどの仕事着に使われてきました。というのも、藍染めには、「繊維を強くする」「防虫効果(野良着がマムシよけになる)」「紫外線をカットする」などの利点があるからなのです。単に見た目を鮮やかにするためだけではなく、昔の人は植物の機能を生かして暮らしに役立てていたのですね。さらに、藍染めの仕組みについても学びました。今回使用するインジゴ色素は水に不溶であり、そのままでは染色ができません。染色するにはインジゴを溶ける物質に還元させ、染め液を作る必要があります。この染め液を布にしみ込ませた後、空気で酸化させることで、再びインジコに戻すという操作を行います。詳しい説明を受け、藍染めへの興味が深まったところで、さあ、実習のスタートです!!
本実験では化学的に合成された市販のインジコを使います。
1) インジコ500mgを300mlのビーカーに入れます。
2) このビーカーに水10mlを入れた後、水酸化ナトリウム2gを入れ、湯浴中で70-80℃に温めながら水酸化ナトリウムを溶かします。
※水酸化ナトリウムはとても危険な薬品のため、慎重に扱います。
3) これに水20mlを加え、さらに70-80℃に温めながらハイドロサルファイト6gを入れてかき混ぜながら溶かすと、混合物の色が薄緑色になります。
※ハイドロサルファイトによりインジコが還元されました。
4) ゴム手袋をして、この中に木綿の布を浸し、1-2分後にピンセットで取り出し、十分水洗いする。



水洗いを始めると、実習室の至るところで大きな歓声が上がりました。感動・・・、うすい緑色だった布がみるみるうちに鮮やかな藍色に変わっていくのです!!実際にこの変化を目の当たりにしたことで、皆さん、藍染め染色の仕組みについてより深く理解できました。


蛍光編 – 光合成色素を見てみよう -
植物の葉の中で、太陽のエネルギーを利用して養分を生産しているのが光合成色素。これは特殊な光(紫外線)を当てると光って見えることから、天然の蛍光物質ともいえますね。実際にどういう風に見えるんだろう??今回の実験では、パセリから光合成色素を取りだして、光る様子を観察します。


本実験では“クロマトグラフィー“と呼ばれる方法で、パセリの光合成色素を分離しました。パセリから取り出したクロロフィルは、ブラックライトという紫外線を出すライトの下で見ると赤く光って見えるのです。今回参加した皆さんはクロロフィルが赤く発光することを初めて知ったようで、驚きとともに、植物の機能ってすごい!!って改めて実感することができました。
また、こういった現象は蛍光と呼ばれていますが、実際に私たちの身の回りにも沢山の蛍光物質が存在しています。参加者の皆さんの持ち物の中から蛍光物質を探してみましょう!!

蛍光ペンだけではなく、紙幣や定期券までもが色々な色に光りました。ものによって様々な色に光りましたが,中には普通は何も見えないのに,ブラックライトを当てると光るものもありました。これらの実験を通して,身の回りには様々な科学の力が役立っていることが分かりました。
<午後>
遺伝子DNAに関する科学実験
はじめに、DNAと遺伝子、PCR法の原理・装置に関する説明を受けました。
遺伝子工学の発展に大きく貢献しているPCR法。これは微量なDNAを短時間のうちに1×107以上に増幅する技術です。
DNAによるイネの品種判別をしよう
DNAの塩基配列の違いにより、イネの品種判別をします。
イネの3品種(1:コシヒカリ、2:ヒノヒカリ、3:あきたこまち)
アガロースゲル電気泳動で、PCR産物の大きさの違いや有無により品種判別を行います。PCR産物(サンプル)は3品種のコメ粒から抽出したDNAを鋳型に増幅させたもので、今回は予め準備していたものを使います。
-
アガロースゲル電気泳動とは??
アガロース(主成分は寒天)のゲルを使用した電気泳動により、核酸を分子量に応じて分離する方法。核酸分子は、それぞれ固有の大きさ(長さ)と荷電を持っている。核酸の場合、荷電の個数は分子の大きさに比例する。分子量の大きいものほど流れにくく、小さいものほど流れやすいため、分子量に応じて核酸を分離できる。核酸はマイナス電荷(リン酸基)をもつため、プラス極に向かって流れていく。→生物体から抽出したDNAや、PCR増幅産物確認のために、電気泳動を行います。
電気泳動装置にアガロースゲルをセットし、Loading dyeで調整したサンプルをゲルのウェルに注入していきます。このとき、ピペットの先でウェルを突き破らないよう慎重に操作するのが大変でした。サンプル注入後、電気泳動を開始です。20分後スイッチを止め、ゲルを取り出しエチジウムブロマイド(EtBr)入りのタッパーに移し、約40分間染色します。その後、トランスイルミネーターにゲルを乗せ、UVランプを点灯させると・・・キラキラと輝くバンドの出現です!!もちろんこの結果は写真で撮影しました。


実験内容としてはかなり難しかったようですが、PCR産物のDNAの大きさの違い(バンドの多型)を視覚的にみることで、イネの品種判別は遺伝子レベルで可能であることを学びました。
参加者の感想
-植物の機能を生かした科学実験-
(中学生)
- 昔からのものや身近なものを使って実験を行い、理解しやすく楽しかった。
- 先生の話がとても面白かった。こういうことを知っていると理科の時間に理解が深まって楽しい!!
- ブラックライトを使った実験が心に残った。
- 今回藍染めをした布を大切にしていきたい。
(高校生)
- いつも不思議に思っていた蛍光の仕組みを知ることができて良かった。
- クロマトグラフィーやブラックライトの反応がとても不思議で面白かった。もっと色々なものを色素分けしてみたい。
- 説明が分かりやすく、また、内容が豊富で面白かった。普段なかなかできない実験ができて良かった。
(教員等)
- 藍染めは、生徒も喜びそうなので、学校へ持ち帰り是非やってみたい!!
- (蛍光色素が)ブラックライトを当て、光ることは知っていたが、実際に見たのは初めてでびっくりした。授業でも使ってみたいです。
- 藍染めの酸化還元反応は学校でも出たところです。是非利用したいです。
- 今回教えて頂いたように、植物がどのように身の回りに活かされているかを生徒たちにも分かりやすくワクワクするように伝えられたらと思いました。
-遺伝子DNAに関する科学実験-
(中学生)
- かなり難しかったが、人や動物の他にコメにまでDNAがあるのには驚いた。
- かなりハイテクな機器を使った実験は滅多にできないので、とても良い経験になりました
- イネの品種判別ではっきりと沈殿が見えたのがすごいと思いました。
- 今まで考えたこともないことがテーマで興味深かったです。
(高校生)
- 意味も分からず見ていた科学捜査研究所のドラマなども、今後は意味を理解して見られると思いました。
- 少し説明が難しかったが実験は楽しかった。学校ではなかなかできない実験をまたやってみたいです。
- 肉眼で見られるレベルでDNAが見れるとは思わなかった。不思議なことが分かるときは本当に楽しい!!
- もっとこの分野を勉強して講座を受けたいと思いました
(教員等)
- 専門的で難しかったが理解深まる内容で面白かったです。
- DNAについては知識がなく、今回実際に抽出のやり方をみられただけでも収穫でした。
- 知れば知るほど興味が沸いてきた。学校では経験することのできない実験を行う機会を与えてくれたことに感謝です。
- 検証することのプロセスの大切さ、実験結果の重要性を知りました。
- 「生物基礎」はDNAが内容に盛り込まれ、このような実験が今後ますます必要になると思います。
主催者報告
今回は,初めて中高生と教員を対象とした専門性の高い公開講座を大学で実施しました。これらの講座を通して,幅広い年齢層に対して科学への興味・関心を高めてもらったことは最大の成果となりました。また、子供たちのサイエンスに対する興味・関心を高めるためには、五感にうったえることが非常に有効であるため、これを考慮して、今後も新しいテーマを増やしながら、学校現場でもできる楽しいバイオ実験教材を提供していきたいと考えています。
ご指導頂いた先生方
伊藤 克治 教授 (植物の機能を生かした科学実験)
山崎 聖司 准教授 (遺伝子DNAに関する科学実験)